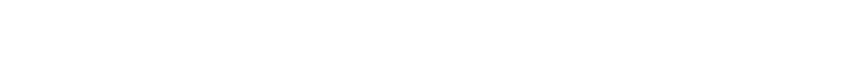相続問題では、様々な専門用語が用いられます。こちらでは、多用される専門用語を解説していきます。
■生前贈与
生前贈与とは、相続が発生する前、つまり生前に子や孫に財産を贈与することです。
生前贈与は、基本的には、相続税がかかる遺産を減らすための節税対策として行われます。
そこで主に用いられるのは、「暦年贈与」という贈与方法です。
暦年贈与とは、受け取る人が1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えなかった場合、贈与税が発生しない制度のことをいいます。
この制度を活用すれば、贈与した人数×110万円×贈与した年数分、無課税で贈与することができます。
子や孫に財産を遺しながら、相続税の課税対象となる財産を減らすことで、相続税を抑えることができるということです。
他にも、教育資金一括贈与特例や、住宅取得資金贈与といった制度を活用して、相続税を抑える生前贈与の方法があります。
生前贈与を行えば、特定の人に対して特定の財産を遺すことができます。
遺言書を作成した場合であっても、不備があると被相続人の意思を完全に反映することができません。
しかし、生前贈与では、遺したい財産を指名した相手に確実に承継することができることに、大きなメリットがあるといえます。
■遺言書
遺言書とは、死後の財産の処分の方法や、誰に未成年の子どもの世話をして欲しいかなどを明記した、法的な書類のことです。
一般的な遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
正しい形式の遺言書が作成されていれば、相続人は、遺言書に従って遺産を分割しなければなりません。相続人の話し合いよりも、遺言書の内容が優先されます。
しかし、遺言書に不備があれば、遺言書としての効力を失って、故人の意思が相続に反映されない場合があります。
遺族が相続争いを起こすことを防ぐためには、正しい遺言書を遺すことが重要だといえます。
遺言書の種類によって、作成方法や保管方法、検認の要否、作成費用等が異なります。
●自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が自ら紙に書き記す遺言書のことです。
特別な手続きなしに作成することができ、費用もかからないのが特徴です。
作成にあたっては、遺言者が遺言全文・日付・氏名を手書きで自筆した上で、押印をする必要があります。ただし、遺言書に添付する財産目録については、自筆せずにPC等で作成しても構いません。
遺言書は、内容に曖昧なところがある、遺言書の内容の一部が自筆されていないなどの不備があれば、遺言としての効力を失ってしまうため、注意しなければなりません。
簡単に作成することができるのが自筆証書遺言の特徴ですが、せっかく遺言書を準備しても不備があれば遺言書の効力が認められず、作成した意味がなくなってしまう可能性があるため、専門家に相談してアドバイスを受けることが望ましいといえます。
また、相続人が自筆証書遺言を発見した場合、勝手に開封してはならず、家庭裁判所で検認手続きを行わなければなりません。
ただし、2020年7月10日から始まった、自筆証書遺言を法務局が保管する制度を利用すれば、家庭裁判所の検認が不要になります。
●公正証書遺言
公正証書遺言とは、二人の証人の立ち会いのもと、公証役場で公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する遺言です。
公証人が作成するため、遺言の書式が誤っている等の理由で無効となることがなく、確実に有効な遺言を作成することができます。
また、作成した遺言書は公証役場で保管され、遺言者にはそのコピーである謄本が交付されます。遺言者が謄本を紛失しても、公証役場で再発行することが可能です。また、遺言書を誰かに隠されたり、偽造や変造される恐れがありません。
そして、開封にあたっての検認手続きを行わずにすぐに遺産相続を開始することができます。
●秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が自分で用意した遺言書を公正役場に持ち込み、二人の証人の立ち会いのもと、公証人が遺言書の存在を保証する形式です。
公正証書遺言のように公証人と証人に内容を公開しない手続きであるため、誰にも遺言の内容を知られたくない場合に有用だといえます。
しかし、検認手続きが必要であり、遺言書の内容や書式に不備があった場合は、秘密証書遺言の手続きを行ったにもかかわらず遺言内容が無効となってしまう場合があります。
このように、費用や手間がかかる割にメリットが少ないため、実際にはあまり使用されていません。
■(公正証書遺言や秘密証書遺言作成の際の)証人
証人には誰でもなれるわけではなく、証人となれない人が立ち会った公正証書遺言等は、無効となる可能性があります。
証人となれない人は、民法974条に定められています。
(証人及び立会人の欠格事由)
第974条
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
証人となれる人に依頼することができない場合でも、弁護士事務所や司法書士事務所等に相談した場合は、証人を用意してくれる場合がありますし、公証役場に証人が見つからない旨を相談すれば、証人となれる人材を紹介してもらうことができます。
その場合、証人の交通費や日当は必要になります。
■遺言執行者
遺言執行者とは、遺言の内容を正確に実現するために必要な手続きを行う人のことをいいます。
相続財産目録の作成、金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義変更手続きなど、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為を行う権限があります。
遺言執行者は、遺言書の中で指定される場合や、遺言者が死亡した後に家庭裁判所で選任される場合があります。
遺言者が、相続人に遺言執行者になってもらうことに不安がある場合は、専門家に遺言執行人となってもらうよう指定することもできます。
■検認
検認とは、相続人に対して遺言書の存在およびその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3種類の遺言書の形式のうち、検認が必要とされるのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言です。
公正証書遺言については、原本が公証役場で保管されることから改ざんの恐れがないということで、検認を受ける必要はありません。
ただし、自宅で保管する自筆証書遺言には検認が必要ですが、2020年7月10日から始まった、自筆証書遺言を法務局が保管する制度を利用すれば、家庭裁判所の検認が不要になります。
故人の家で封のされた遺言書(自筆証書遺言と秘密証書遺言)が見つかった場合、検認を受けずに勝手に開封してしまうと、5万円の過料が科されてしまいます。
勝手に開封したからといって遺言書が無効になるわけではありませんが、偽造や変造をしたのではないかと疑われてしまう場合があります。
検認手続きをするには、家庭裁判所に検認の申し立てをする必要があります。
■遺産分割協議
故人が有効な遺言書を遺していない場合には、遺産分割協議が行われます。
遺産分割協議とは、相続人全員で、遺産を誰がどのような割合で、どの財産を受け継ぐのか、話し合いをすることをいいます。
遺産分割協議に先立って、相続する全財産がどのくらいあるのか、誰が相続人となるのかを確認します。遺産分割の合意が成立するには、相続人全員の合意が必要であるため、すべての相続人を確定しなければならないのです。
相続人同士の話し合いだけでは解決できなかった場合は、家庭裁判所において調停委員が相続人の間を仲介したり、家事審判官が具体的な解決策を提案したりしながら遺産分割協議を行う、「調停」という手続きが行われます。
調停が不成立となった場合は、家庭裁判所での「審判」を行います。審判では、裁判所が法律に従って強制的に分割方法を決定します。
●遺産分割協議書
遺産分割協議書とは、相続人が話し合った遺産分割協議の内容を書面にまとめたものです。
遺産分割協議書を作成することが望ましい理由は、まず、後のトラブルを防止するためです。
協議の時には同意していた相続人が、決まった内容に後から異議を唱えた場合など、遺産分割協議の内容を書面で残しておかないと、紛争が蒸し返されて、相続争いが長期化するおそれがあります。
次に、実際の分割手続きで必要な場合に提出しなければならない場合があるからです。
遺産の中に不動産が含まれていたら、不動産の相続登記をしなければなりません。そこで、法定相続分と異なる割合で相続登記を行う場合には、遺産分割協議書を提出することが求められることがあります。
また、相続税の申告の際に提出が求められる場合もあります。
遺産分割協議書に記載する事項は、相続財産の具体的な処分内容です。
また、遺産分割協議を行った後に財産が発見される場合に備えて、「もし協議の時点で判明していない財産が後に発見された場合にどうするか」ということも事前に決めて、遺産分割協議書に記載することが望ましいといえます。
■遺留分
遺留分とは、法定相続人に認められる、最低限の相続分のことです。
遺言書の内容よりも、遺留分の権利の方が優先されます。
遺留分が認められる人は、以下の通りです。
・配偶者
・子およびその代襲者等
被相続人(故人)の子が法定相続人になる場合は、子に遺留分が認められます。
被相続人の子がすでに死亡している場合は、孫が子を代襲相続して、孫に遺留分が認められます。
・親、祖父母等の直系尊属
被相続人に子も孫もいない場合は、親が法定相続人になり、親に遺留分が認められます。
兄弟姉妹およびその代襲者は、法定相続人になることはあっても、遺留分は認められません。
●遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは、遺贈や生前贈与、遺言書の内容で、遺留分が侵害されてしまったときに、他の相続人に遺留分に相当する金額を請求することをいいます。
遺留分侵害額請求は、遺産そのものを取り戻すものではなく、侵害者に金銭的な補償を求めることができるものです。
したがって、遺留分を侵害した贈与等がなされた財産が、金額に換算すればいくらであるのか評価することが必要です。
■相続放棄
何の手続きもなく相続を行えば、相続人は故人の財産も債務も全て受け継ぐことになります(単純承認)。すなわち、故人が膨大な額の借金を抱えていた場合は、相続財産と自分の財産を合わせても借金の返済ができない状況に陥ってしまうことになります。
そこで、「相続放棄」を行えば、全ての遺産の相続を放棄することができ、借金を相続しないで済みます。
相続放棄をすれば故人の借金から解放されることは大きなメリットですが、財産を一切相続することができません。
例えば、現在、親所有の家に住んでいる場合、親が死亡して相続が開始された時に、相続放棄を選択すれば、住居や家具などを含むすべての遺産が相続できず、家を出ていかなければならないということになります。
相続放棄を行える期間は原則として3ヶ月間しかありません。その間に相続財産・債務額の調査を行ったり、他の相続方法との比較などを行ったりして、相続方法を決定する必要があります。
■限定承認
故人の借金が多額である場合の相続方法として、「限定承認」という選択肢もあります。
限定承認では、故人の借金が多額であっても、全ての財産を手放さなくても相続で得た財産を限度として、故人の借金を弁済する相続方法です。
例えば、故人に2000万円の債務があって、500万円の家だけを限定承認で相続した場合は、500万円分の債務は債権者に弁済しなければなりませんが、残りの1500万円については弁済しなくて構わないということになります。
多額の借金を背負わずに大事な財産を受け継ぐことができる点が、限定承認のメリットです。
しかし、相続人全員の同意が必要である上、手続きが非常に煩雑で時間と手間がかかるため、実際には相続放棄が選ばれることが多くなっています。
相続放棄と同じく、限定承認を行える期間は原則として3ヶ月間しかありません。