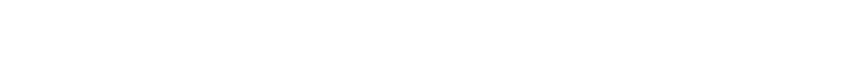985条(遺言の効力の発生時期)
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
●遺言は遺言者の死亡の時点から効力が発生します(985条1項)。そのため、受遺者が遺言者の死亡時点に存在していない場合には、遺贈は効力を発生しないことになります(994条1項)。
なお、受遺者が遺言者の死亡時点には存在していたものの、遺贈の承認を行う前に死亡してしまった場合には、遺言者の死亡時点には存在していたことになりますので、遺贈は効力を生じ、受遺者の相続人がその権利を有することになります(988条)。
停止条件付遺言とは、遺言の効力発生に対して条件が付いている遺言のことをいいます。停止条件付遺言の場合、遺言の効力発生は条件が成就した時点からとなるため(985条2項)、条件の成就前に受遺者が死亡した場合には遺言は効力を生じないことになります(994条2項)。
986条(遺贈の放棄)
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
●特定遺贈の受遺者は、遺言者の死後いつでも遺贈の放棄をすることができます(986条1項)。これに対し、包括遺贈の場合は、包括遺贈者は相続人と同様の権利義務を有するため、相続の放棄と同様に遺贈の放棄には家庭裁判所への申述が必要となります(915条)。
遺贈が放棄された場合、その効力は遺言者の死亡時点にさかのぼって発生し(986条2項)、受遺者が受け取るべきであった相続財産は相続人に帰属することになります(995条)。
987条(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。
●相続人や遺言執行者などといった遺贈義務者やその他の利害関係人は、受遺者に対して相当の期間を定めて遺贈の承認・放棄の催告を行うことができます。この時、受遺者が期間内に遺贈義務者に対して意思を表示しない場合は、受遺者は遺贈を承認したものとみなされます(987条)。
988条(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
●遺贈には相続権が認められているため、受遺者が遺贈の承認または放棄をする前に死亡した場合には、受遺者の相続人が自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認または放棄をすることができます(988条)。
なおこの場合でも遺言者がその遺言に別段の意思を表示していた場合には、その意思に従うことになります。
989条(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
2 第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
●一度行った遺贈の承認及び放棄は撤回することができません(989条1項)。
一方、遺贈の承認・放棄の取消しについては、【相続の承認・放棄の取り消しに関する規定】(919条2項・3項)が準用されるため認められています。この場合の取消権は、追認をすることができる時から6か月間、あるいは相続の承認・放棄の時から10年経過すると時効になってしまいます(919条3項)。
990条(包括受遺者の権利義務)
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
●遺贈には相続人と同様に遺言者の相続財産を割合として遺贈するケースである「包括遺贈」と、特定の財産を指定して遺贈するケースである「特定遺贈」の二つがあります(964条)。
このうち、包括遺贈における受遺者(包括受遺者)は、相続財産を割合として遺贈されるという性質上、相続人と同一の権利義務を有することになります(990条)。
991条(受遺者による担保の請求)
受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。
●受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができます(991条)。
また、この規定は停止条件付遺贈の場合も同様で受遺者は、条件が成就するかどうかが定かでない期間であっても、遺贈義務者に対して担保を請求することができます(同条)。
992条(受遺者による果実の取得)
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
●遺贈の受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時点から「果実」を取得することができます(992条)。
ここでいう果実は、リンゴやみかんなどといった果物のことではなく、法律用語としての果実を指します。
法律用語としての果実とは,不動産などの物から生じる利益・収益のことをいいます。法律用語としての果実には、Ⅰ.物の用法に従い収取する産出物である天然果実(88条1項)とⅡ.物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物である法定果実(同条2項)の二種類があります。
そのため、遺贈の対象物がアパートなどといった不動産であった場合、受遺者は遺贈の履行を請求することができる時点から、 アパート(遺贈の対象物)に生じる家賃(果実)などを取得することができます。
993条(遺贈義務者による費用の償還請求)
第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。
2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。
●留置権者による費用の償還請求(299条)は遺贈義務者に関しても準用されるため、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合、受遺者はその費用を償還する必要があります(993条、299条)。
ここでいう費用には必要費(目的物の管理・保存等に要される費用)と有益費(目的物の価値を増加させるために支出された費用)が含まれます。
このうち、有益費に関しては、遺贈義務者は、その支出による価値の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額または増加額を償還させることができます(299条2項)。
また、遺贈義務者による費用の償還請求の場合、果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度での償還請求を行う必要があります(993条2項)。
994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
995条(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
●985条(遺言の効力の発生時期)でも説明した通り、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合には、遺贈の効力は発生しません(停止条件付遺贈の場合は条件の成就以前に受遺者が死亡した場合)(994条)。
このようなケースを含め、遺贈が効力を生じない場合や、受遺者が遺贈を放棄するなどしてその効力が失われた場合には、受遺者が遺贈によって受け取るべきであったものは、相続人に帰属することになります(995条)。
996条(相続財産に属しない権利の遺贈)
遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。
997条
相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
●他人の権利を目的とした遺贈は原則無効になります(996条)。そのため、遺言を作成した時点では遺言者のものであった場合でも、遺言の効力が発生するまでの間にその権利が売却・贈与などを経て他人の権利になっていた場合では、その遺贈は効力を生じません。
しかし民法では例外的に、他人の権利を目的とした遺贈であっても、権利の帰属が誰にあるかにかかわらず遺言者がその権利を遺贈の目的とした遺贈の場合、その効力は認められるという規定を設けています(996条但書)。
具体的な事例としては、遺言者が十分な金銭を持っており、受遺者に対して何らかの具体的な権利(他人に属する不動産の所有権など)を遺贈したいと考えているが、自らが生存している間にその権利を取得することが困難である場合などがあげられます。
996条但し書きの規定に則り、他人の権利を目的とした遺贈が有効と認められる場合、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負います(997条1項)。
ここでもし遺贈義務者が遺贈の目的とされた権利が取得できなかった場合、あるいはその権利を取得するために過分の費用を要する場合には、遺贈義務者は受遺者に対して、遺贈の目的とされる権利の価額を弁償する必要があります(遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います)(997条2項)。
998条(遺贈義務者の引渡義務)
遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
●遺贈義務者は、遺贈の目的である物や権利を相続開始の時点(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時点)の状態で受遺者に引き渡し、あるいは移転する義務を負います(遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います)(998条)。
そのため、相続開始以後、遺贈の目的となるものに損傷等が発生した際には、遺贈義務者は修繕等を通じて目的物を相続開始時点の状態に戻す義務を負うことになります。
999条(遺贈の物上代位)
遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。
1000条 削除
1001条(債権の遺贈の物上代位)
債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。
2 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。
●遺贈の目的物が遺言者の死亡時点において相続財産に属さなかった場合、遺贈は原則無効となります(996条)。
しかし、遺言者の死亡以前に遺贈の目的物が滅失した場合などであって、そのことにより遺言者が第三者に対して償金を請求する権利を有している場合には、その権利が遺贈の目的と推定され遺贈は有効となります(999条1項)。
例えば、「遺言者が高価な絵画を遺贈の目的物としていたところ、第三者が誤ってその絵画を紛失してしまい、遺言者がその第三者に対して損害賠償請求権を有した」というケースの場合、当該受遺者は遺言者が第三者に対して有する損害賠償請求権を遺贈の目的と推定して遺贈を受けることになります。
●債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中にある場合には、その物を遺贈の目的としたものと推定されます(1001条1項)。例えば、遺言者が購入した不動産につき、所有権に基づく不動産引渡請求権を遺贈の目的として遺言を作成した場合、そののち遺言者に対して不動産の引き渡しが行われ、遺言者死亡後にもなお当該不動産が相続財産に含まれるケースにおいては、遺贈の目的とされた債権(所有権に基づく不動産引渡請求権)を元に弁済された当該不動産が遺贈の目的として推定されることになります。
また、債権のうち特に金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定されることになります(1001条2項)。そのため、遺贈の目的とされた金銭債権が遺言者の死亡以前に弁済され、遺言者がその弁済された金銭をすでに使いきってしまっている場合であっても、遺贈の目的とされた金銭債権の債権額が遺贈の目的物であると推定されるため、遺贈義務者はその金額を受遺者に遺贈する義務を負います。
1002条(負担付遺贈)
負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
1003条(負担付遺贈の受遺者の免責)
負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
●負担付遺贈とは、一定の義務を負担しなければいけない条件がついた遺贈のことをいいます。
負担付遺贈には「高齢の妻の代わりに畑の管理をしてくれるなら土地を遺贈する」や、「残りのローンを全て払ってくれるなら住宅を遺贈する」などといったケースが含まれます。
負担付遺贈を受けた場合、受遺者は遺贈につけられた負担を履行する義務を負います。しかしこの場合において、遺贈された財産以上の負担を受遺者に負わせることは不都合であるため、民法では負担付遺贈の受遺者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ負担した義務を履行する責任を負うと定められています(1002条1項)
負担付遺贈の受遺者が遺贈の放棄をした場合には、負担の利益を受ける予定だった人が自ら受遺者になることが可能です(1002条2項)。
ここでいう負担の利益を受ける予定だった人には、「高齢の妻の代わりに畑の管理をしてくれるなら土地を遺贈する」のケースでは、代わりに畑の管理をしてもらう(負担の利益)はずだった妻などが該当します。
また、負担付遺贈の目的の価額が、相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少した場合には、受遺者はその減少の割合に応じて、負担した義務から免れます(遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います)(1003条)。
例えば「残り500万円の住宅ローンを全て支払う」という負担がつけられ「3000万円の不動産」を遺贈された負担付遺贈のケースにおいて、遺留分回復の訴えにより遺贈の目的物の1割である300万円が受遺者から弁済された場合、受遺者は「残り500万円の住宅ローンを全て支払う」という負担の内、減少した遺贈の目的の価額の割合と同等の割合である50万円分の負担義務から免れることになります。