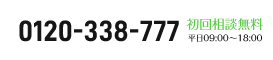こんなトラブルがあるかも?1人のときの問題点
自分で抱えすぎて、売上ダウンという事態も
資産づくりに関するさまざまな方法をお伝えしてきました。
個人で取り組むべきこと、会社で実施すべきこと、両者の立場から取り組むべきこと。いずれも実践可能な方法ですが、だからといってすべてを経営者が1人で行うというのは難しい話です。
将来を見据えて考えれば、いますぐに取り掛かりたいことでも、売上の維持・拡大、従業員の指導や教育といった本業に関する課題が山積みで、動きたくても動けないというのが本音でしょう。
もちろん、経営者自身がセミナーに参加したり、相続税対策や資産づくりの勉強をするのがダメというわけではありません。ですが、本業にかける時間が削られれば削られるほど、会社の売上がダウンする可能性は上がります。
一度売上が落ちてしまってから、元の状態に回復させるまでには、いままで以上の労力が必要です。
そんな悪循環に陥らないためには、いったいどうすべきか。
その答えが、「プロ」に任せるという発想です。
昔から「餅は餅屋」と言います。右も左もわからないなか、自分で勉強して、かなりの時間と労力を使うくらいであれば、それは本業の「会社経営」に使っていただき、プロにすべてを任せてしまえばいいのです。
専門家であれば、間違いなくスピーティーに結果を出してくれるはずです。
あなたの置かれた状況を的確に把握し、いまの状況にあった最適解を導き出してくれる存在なのです。
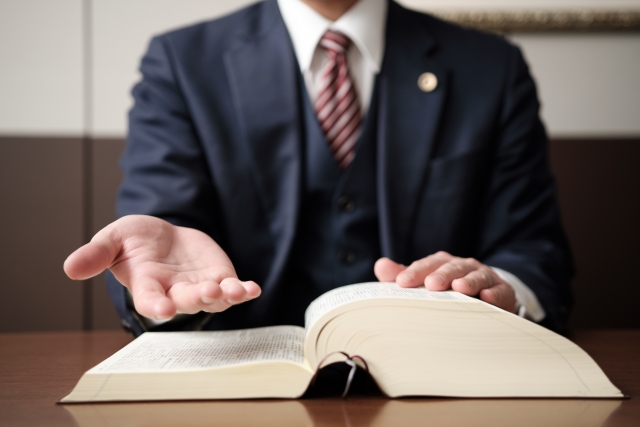
心強い味方はやっぱりプロしかいない
それぞれの強みを把握せよ
では、ひと口にプロといっても、誰に何をお願いすればいいでしょうか。資産づくりのプロに関してそれぞれの特徴を整理しておきましょう。
まずは「司法書士」です。
司法書士は登記のエキスパートです。
会社設立時の登記だったり、自宅や土地の購入時にお世話になった方も多いはずです。司法書士事務所を訪れる場合は、
「相続財産のほとんどが不動産で、金融資産は少額。相続税は基礎控除内で済むが、遺産分割協議で相続人同士が少しもめるかもしれない」というケースに向いています。
民法や家事審判手続きに精通している優秀な人であれば、過去の判例に基づいてわかりやすく説明してくれたり、上手に事を収める術を身につけているかもしれません。
次に「行政書士」です。
行政書士はあらゆる法律業務に従事しているプロです。
“町の代書屋”として頼りになる存在で、携わる仕事の種類は1万を超えます。
ただし、人によって何を専門とするかが分かれるため、事前に何を得意とするか確認しておくとスムーズです。行政書士事務所を訪れる場合は、
「相続財産」は比較的少額で、相続人同士で話し合いはできているため、後々のことを考えて法律に則って手続きをしておきたい」というケースに向いています。
遺言書や遺産分割協議書の作成がメインになりますので、書類関係で困ったときに尋ねると力になってくれるはずです。
続いて「弁護士」です。
弁護士は法律全般のプロです。
法律に関するあらゆる知識をもっています。ただ、最近は細分化が進み、交通事故専門、医療事故専門、企業法務専門と、分野が多岐に分かれます。
弁護士資格をもっていると、税理士の職務を行えるため、一挙両得を期待して相談に訪れる人も少なくないでしょう。
ただし、仕事ができるのと、税務を専門としていて知識が多く、豊富な経験をもっているかどうかは別の話です。もし、弁護士事務所を訪れる場合は、
「相続財産が多額ですでにもめている。費用はかかってもいいので、できるだけお多く財産を手に入れられるようにしたい」というケースに向いています。
最後に「税理士」です。
税理士は税務の専門家です。相続税や贈与税といった節税対策をはじめ、あらゆる税務関連に課題に応えてくれるでしょう。税理士は登録するだけで行政書士になることもでき、相続を専門にしている税理士は、税理士兼行政書士として事務所を構えているでしょう。税理士事務所を訪れる場合は、
「少なく見積もっても相続財産が基礎控除を超えそうで、将来の相続税が心配だ」というケースがいいでしょう。
また、ここで紹介した専門家以外の協力も必要になるでしょう。
理想は、各分野のプロフェッショナルを紹介してくれそうな“まとめ役”を見つけて相談することです。「登記」だと司法書士、「裁判」だと弁護士、「不動産の評価」だと不動産鑑定士というように、相談内容に応じて求められる知識は変わります。
とりわけ相続に関する相談は
その性質上、どうしても一歩踏み込んだ内容にならざるを得ません。相手が知識や経験を有しているかどうかも大事ですが、それ以上に相手の人柄や相性も重要になります。
そのあたりをきちんと見極めて相談してみるようにしましょう。

節税対策ができる税理士を探そう
税理士にも専門分野がある
さきほど税理士は税務の専門家と言いましたが、じつは税理士にも「専門分野」があります。医師に「内科医」「外科医」「脳外科医」とあるように、税理士も「相続税法」「酒税法」「固定資産税」などと専門分野をもっているのです。
これは税理士になるための試験科目が分かれていることに起因します。
試験科目は全部で11科目ありますが、必須は「簿記論」「財務諸表論」の会計科目。1科目以上の選択必須となるのが「法人税法」「所得税法」です。
一方、「相続税法」「消費税法」「固定資産税」「事業税」「住民税」などは選択科目で、すべてに精通していなくても税理士になれるのです。
税理士事務所で「○○に強い!」「○○の相談はお任せ!」といったコピーが目立つのも、自分の専門分野をアピールしているから。
これは裏を返せば、専門外のことを相談しても最低限のことしかわからず、気体に応えられないこともあるといえるでしょう。そのため相続の相談をしてサポートを受けるのであれば、「相続税」を専門とする税理士を探すことです。
理想は「近隣で、親身に相談に乗ってくれる、相続税を専門」とする税理士です。探し方としては次のような方法があります。
●自社の顧問税理士に紹介してもらう
●経営者仲間の顧問税理士を紹介してもらう
●銀行や保険会社の営業マンに紹介してもらう
●税理士会の名簿から紹介する
●インターネットで検索する
経験豊富な人ほどさまざまな分野の専門家と太いパイプをもっています。横の人脈も多いでしょう。
インターネットで「地域名相続税理士」などと検索をすれば、こちらが意図する最寄りの税理士事務所も見つかるはずです。
電話やメールで事情を話してアポイントを取り、親身に相談に乗ってくれるかどうかを見極めてください。お問い合わせ欄などがあれば、事前に「相続税」を専門としているかどうかを尋ねてみるのも1つの手です。
「そんなことを直接聞くのは失礼にならないか・・・・・・」
「機嫌を損ねて親身に相談に乗ってもらえないのではないか・・・・・・」
そんな心配をする人もいるかもしれませんが、相手もプロです。
快く相談に乗ってくれるはずですし、たとえ専門分野ではなくても横のつながりから専門分野の方を紹介してくれるでしょう。
むしろ依頼を引き受けてから、「自分の専門分野ではなかった・・・・・・」と発覚して困るよりは事前に相談内容を把握し、これなら自分でも十分に相談に乗ることができると確信したいはずです。
これまで繰り返し述べてきたように、資産づくりで成功する秘訣は「減らさないこと」です。個人の節税も、会社の節税も、両者の立場を活用した節税も、事前準備をして、早め早めに動くことが大切です。そして、そのキーマンとなるのが、サポートをしてくれる「いい税理士」です。
ぜひここまでの記事を活用して、資産づくりにつながる節税対策を行ってください。
いい税理士との出会いが、節税効果を最大限にしてくれるはずです。