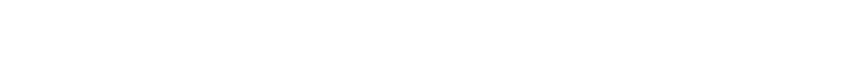高齢化社会の進展と共に、相続のことでお困りの方や、遺言や生前贈与を残すかどうかなどでお悩みになる方も増えています。これに関連して、亡くなられた方が遺言を残していた場合、ご自身や近親者が相続できる財産がとても少ない内容でも、少しでも相続財産を確保できる制度があります。これを遺留分制度といいます。2018年(平成30年)の民法(相続法分野)改正によってこの制度の内容が変わりました。この記事では、遺留分制度がどういうものかと、改正のポイントについてご説明します。
■遺留分制度とは
遺留分制度とは、相続の場合に相続人を保護するため、相続財産の一定割合の留保を認める制度のことです。本来、人は亡くなった後に自分の財産を誰に譲るのかを決めるのは自由で、どのような内容の遺言も残すことができます。そのため亡くなった方が遺言を残していた場合、遺産を誰にどのように分けるかは、基本的に遺言に従うのが原則です。しかし亡くなった方の近親者の相続への期待を保護し、また、被相続人死亡後の遺族の生活を保障するため、最小限度の財産は法定相続人に保障させようというのが、遺留分の制度になります。
遺留分制度とは、相続の場合に相続人を保護するため、相続財産の一定割合の留保を認める制度のことです。本来、人は亡くなった後に自分の財産を誰に譲るのかを決めるのは自由で、どのような内容の遺言も残すことができます。そのため亡くなった方が遺言を残していた場合、遺産を誰にどのように分けるかは、基本的に遺言に従うのが原則です。しかし亡くなった方の近親者の相続への期待を保護し、また、被相続人死亡後の遺族の生活を保障するため、最小限度の財産は法定相続人に保障させようというのが、遺留分の制度になります。
■遺留分権利者と遺留分の割合
●遺留分権利者
遺留分の保障を受けることができる者を遺留分権利者と言います。遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人(被相続人の配偶者・直系卑属及び直系尊属および子の代襲相続人)が対象で、法定相続人でも兄弟姉妹は入らないことに注意が必要です。また、妊娠中の方が亡くなった場合、その胎児が生きて産まれたら、その子も遺留分の権利を持ちます。
●遺留分の算定と割合
遺留分の算定については民法1029条から1030条で定められています、まず、贈与または相続開始前1年間の生前贈与の金額と、遺産の総額を合計し、合計金額から債務全額を控除した金額が、遺留分の算定の基礎となる金額です。この贈与は、それ1年以上前の生前贈与であっても当事者が両方ともが遺留分を侵害することを知ってした贈与なら含まれます。また、負担付贈与がされた場合は、負担の価額を贈与の価額から控除して計算します。
また、遺留分の割合(総体的遺留分といいます)は、直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の1/3で、その他の場合は1/2です。これらを遺留分権利者全員で分けます。分けたときの一人当たりの遺留分として、遺留分権利者の法定相続分の割合をかけた金額が実際の遺留分金額(個別的遺留分といいます)になります。
例えば、法定相続人がAとBとCの3人いるとして、Aが被相続人の配偶者であり、BとCは被相続人の子であるとします。被相続人は、亡くなる半年前に生前贈与として2000万円を愛人Xに贈与し、相続開始時点での遺産は3000万円存在するとします。また、債務が1000万円で存在するとします。
この例において、それぞれの金額は以下のようになります。
遺留分の算定の基礎となる金額:2000万円+3000万円-1000万円=4000万円
遺留分合計(総体的遺留分):4000万円×1/2=2000万円
Aの実際の遺留分(個別的遺留分):2000万円×1/2(法定相続分)=1000万円
B・Cの実際の遺留分(個別的遺留分):2000万円×1/2(法定相続分)÷2人=500万円
■遺留分侵害制度の概観
相続開始時点の相続財産から贈与や遺贈を差し引くと、残りの相続財産の価額が遺留分の額に達しない場合には、遺留分が侵害されたことになります。この場合、遺留分権利者と及びその承継人は遺留分を保全するための措置ができます(旧民法1031条、改正民法1046条)。
この返還請求等は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈、新しい贈与、古い贈与の順で及びます。またこれをするためには、遺留分権利者が遺留分侵害の事実を知った時から1年以内、もし遺留分侵害の事実を知らなくても相続開始後10年以内に、相手方に対して意思表示をすることが必要です。
■遺留分減殺から遺留分侵害へ
平成30年の相続法の改正では、遺留分減殺が遺留分侵害に変わったというように言われています。では具体的にはどのような内容の改正なのでしょうか。
改正前民法では、遺留分減殺請求権(旧1031条)が行使されると、減殺の対象である遺贈や贈与は遺留分権利者の遺留分を侵害する限度で効力を失い、遺贈等の目的財産の権利が遺留分権利者に帰属するという効果が生ずるとされていました。
しかしこの規定では、目的財産が受遺者・受贈者と遺留分権利者の共有となってしまいます。その結果、共有物の処分をどうするかめぐって共有者間での紛争につながることが多々ありました。例として、被相続人が長男に1億1000万円超の建物を、長女に預金約1000万円を相続するという旨の遺言を残して亡くなったという事案で、この遺言に不満を持った長女が遺留分減殺請求をした場合、建物が、長女が約2000万円、長男が約9000万円分の持分を有する共有状態となってしまい、1つの建物の所有者が二人いるために処分が複雑になったというケースがありました。
そこで、改正民法は「遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる」(1046条1項)と規定し、目的財産の評価額を基準に、現物ではなく具体的な金銭債権が発生するとしました。すなわち、遺留分侵害額請求によって減殺の対象となる遺贈や贈与は失効せず、遺留分を侵害する限度で金銭債権が発生するという効果が生じる制度に変わりました。具体的には先ほどの例では、長女は長男に2000万円の金銭債権を有するという結論になります。
この改正により、処分の難しい共有状態を回避することができます。さらに、例えば「この建物は長男に処分を決めてもらいたい・商売に使って欲しい」などという、受遺者の意思に素直に従った処分ができるようになりました。またこれに伴い、遺留分減殺と言われていたこの制度は、今後、遺留分侵害というふうに言われることになりました。
なお併せて、遺留分権利者から金銭債権の請求を受けた受遺者または受贈者が、金銭を直ちには準備できない場合を想定し、この場合には,受遺者等は裁判所に対し支払い期限を求めることができるもできるようになりました(改正1047条5項)。これによって、すぐに現金を用意することのできない受遺者または受贈者は、遅延損害金や強制執行を受けることになってしまうという不都合を防ぐことができます。
■まとめ
遺留分制度がどのように変わったかについてご説明いたしましたが、実際にご自身の遺留分はどれくらいでどのように請求していくかというのは、遺言の内容や、受遺者が誰か、受贈者はいるのか、遺産総額によっても変わってきます。もし遺留分や遺言についてお悩みの方がいらっしゃれば、一度弁護士など専門家に相談してみてはいかがでしょうか。