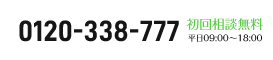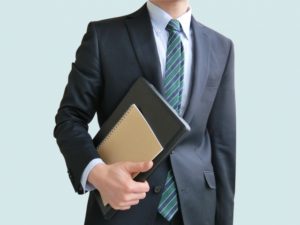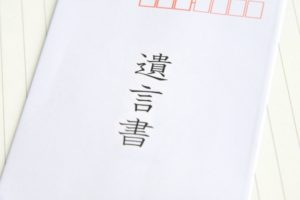相続って何をすればいいの?
相続の基本知識を押さえる
そもそも相続とは、いったい何かをきちんと確認しておきましょう。
相続とは、「被相続人の死亡を原因として、法律で定められた相続人に対して、個人の財産上の権利や義務が包括的かつ一方的に移転すること」です。
これは決して「個人の財産を受け継ぐ」といった漠然としたものではありません。むしろ置かれた状況によって異なるルールが存在します。たとえば、
●遺産分割協議によって財産を受け取るケース
●遺言書のとおりに財産を受け取るケース
●生前に被相続人から財産を譲渡されるケース
いずれの場合もルールに基づいてきちんと手続をしなければ、想定外の税金を納める必要が出てきます。
詳しい解説に入る前に、まずは相続税に関する基本を見ていきましょう。
相続では、財産を残して亡くなった人を「被相続人」、その財産を受け取る立場にある人たちを「相続人」と呼びます。
相続人となれるのは、故人の配偶者や血縁関係にある人。具体的には、子や孫などの直系卑属、兄弟姉妹が含まれます。
この相続人がどれくらいの割合で財産を相続できるかは民法で定められ、法律によって定められた相続人を「法定相続人」と呼びます。
基本的には「配偶者→子→親→兄弟姉妹」の順に相続できます。
被相続人と婚姻関係にある配偶者は常に相続人となります。
法律が定める配偶者は「婚姻届を出している」夫婦に限定されるため、婚姻届けを出していない内縁関係の人は相続人になれません。
子どもが相続人になれるケース、なれないケース
子どもが相続人になれるかどうかは、被相続人との血縁関係の有無によります。

《相続人になれる》
【婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子(=摘出子)】
法律上、子どもは「摘出子」。たとえ出産前の胎児でも生まれたものとして相続権を取得できる。
【内縁関係にある夫婦の間に生まれた子(=非摘出子)】
法律上、子どもは「非摘出子」。ただし被相続人の父親の場合は「認知」が必要。
【離婚した元配偶者の子(=摘出子)】
元配偶者は相続人になれないが、子は被相続人と血縁関係があるため、相続権を取得できる。
《相続人になれない》
【再婚相手の連れ子】
相続人になれない。ただし、養子縁組をすれば相続人になれる。
また、孫は通常、相続人になれませんが、次の場合は相続人になることができます。子どもがいたけれど、すでに他界している場合です。これを「代襲相続」といい、相続する者を「代襲者」あるいは「代襲相続人」と呼びます。
ちなみに子どもも孫も他界し、曾孫がいる場合はその曾孫が相続人になります。
これを「再代襲相続」といいます。
なお、故人が生前お世話になり、血縁以外の人に財産を残したいというケースもあります。たとえば、内縁の妻、恩師、愛人などです。
こうした法定相続人以外に財産を残す場合は「相続」ではなく「遺贈」という形になります。財産を遺贈された人は「遺贈者」と呼びます。あわせて覚えておきましょう。

誤った相続によって資産はこれほど目減りします!
基礎控除を超えたら、あなたも相続税対象者
では、実際に相続が発生したら、どうなるのでしょうか。
平成30年度現在、相続税の基礎控除は「定額控除額+法定相続人加算分」という次の計算式で算出できます。
●3000万円+600万円×法定相続人の数
仮に妻と、子どもが2人いる家族で、父親が亡くなった場合の基礎控除は4800万円です。つまり、4800万円を超えた分は、課税対象となります。
相続税の対象は「不動産(土地、建物)」「預貯金、現金」「株式・投資信託」「動産(車・家具・貴金属等)」「生命保険金・会社の退職金」などがあります。
これらすべてを含めて4800万円とした場合、いかがでしょうか。
会社から少なくない役員報酬をもらって貯金し、一部は株式や投資信託で蓄財、持ち家などの不動産を1つ所有し、生命保険に加入しているだけで、おそらく基礎控除を超えてしまう方が出てくるはずです。そこまで資産をもっていないから相続税は関係ないというのは誤りなのです。
基礎控除を超えた部分は、下記の区分で税金の支払いが発生します(図表①)。
図表① 改正によって、税率はどう変わったか?

まさに事前準備をしていない人ほど、支払う金額が多くなる可能性が高いです。
オーナー経営者だったり、資産を多く保有する方であれば、どれほど多くの税金を訴払わなければいけないかは想像に難くないでしょう。
どうすれば相続を乗り切れるのか?
このような話をすると、「自分の家族は仲がいいから相続でもめない」「まだ若いからいまは考えていない」という声を聴きますが、油断禁物です。
仲がいい家族でも大金が絡むと揉めてしまいますし、突然の病気や事故で遺言が書けなくなったというケースもあります。
主な財産が「不動産」だけの場合、相続税の支払いは確定しているのに、支払う現金がなくて相続人の間で揉めるという例もあります。
実際、相続時にあるトラブルのトップは「不動産の遺産分割」で、毎年1万円件以上が訴訟になっています。
こうしたことからも、相続に関しては悠長にかまえず、事前の対策が非常に重要になってくるのです。
では、何から考えるべきか。まずは簡単に相続対策の流れを整理しておきましょう。

【財産の把握】
最初に「財産目録」を作成します。これは会社でいえば、貸借対照表に該当します。
会社にどれくらいの現金、商品、土地、借金があるのかを把握するのと同じで、故人の財産を正確に把握することが大切です。
【相続人の把握】
続いて、法的な根拠として、「戸籍謄本」を集めます。
相続人が遠方や海外にいる場合は代理申請の印鑑をもらうだけで大変なので、その際は司法書士などの専門家に依頼してもいいでしょう。
【遺言書の用意】
遺言書は2種類あります。被相続人本人が書いた「自筆証書遺言」と、被相続人が生前に公証役場で口述したものを、公証人が筆記して作成した「公正証書遺言」です。
【成年後見制度の活用】
被相続人や相続人が認知症などによって正常に判断できなくなった場合、その判断をサポートする「後見人」を家庭裁判所が選任する制度です。判断能力が失われた人をサポートするのを「法廷後見制度」、まだ判断能力はあり、将来サポートしてくれる人を選ぶのを「任意後見制度」といいます。
【信託の活用】
信託とは、信頼できる相手に自分の財産の名義や管理、処分権を移転させて、財産の運用・管理・処分によって得られる利益を、所定の人物に与える仕組みです。基本的に次の3者によって成り立ちます。
「委託者」財産をもっていて、その財産を信託する人物
「受託者」財産を信託されて、その運用管理等を行う人物
「受益者」信託財産の運用管理等によって出た利益を受け取る人物
【納税資金の準備】
納税資金の準備方法は「生命保険」「持株会社」「退職金制度」の活用が有効です。「自社株の物納」という方法もありますが、これは次の2つの要件を満たす必要があります。
①相続税を払うだけの金銭的余裕がなく、20年延納しても支払うことが困難であると認められるとき
②非上場株式に譲渡制限がついていなく、質権等の担保も設定されていない。また、その所有権をめぐる争いがなく、共有もされていなく、原則として、会社が1年以内に自社株を買い戻すこと
ただし、物納にはメリットやデメリットがありますので、詳しいことは専門家に尋ねてみましょう。
ここまでが一連の相続対策に関する流れです。
では、次からは具体的な節税対策を学んでいきましょう。