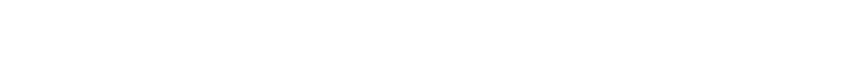民法1042条以下は、遺留分について定めた規定です。遺留分制度とは、遺言や遺贈に関わらず、相続人に対して一定額の相続財産を必ず保障する制度のことです。たとえば、亡くなった方が「長女に全財産を譲り渡す」という遺言を残していたとしても、配偶者や、次女、三女などと言った他の法定相続人も遺留分の限度だけは相続の権利を有していて、その限度において長女に対して請求できるということになります。この制度は、法定相続人が、遺産の相続ができるであろうという期待を保護し、また遺族(相続人)の生活の安定、財産分配の調整の観点から設けられている制度です。では、条文を確認していきましょう。
1042条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
1042条は、遺留分の帰属及びその割合について定めています。
1項はまず、遺留分の帰属、つまり遺留分の権利者が誰なのかを確認しています。
それは、「兄弟姉妹以外の相続人」とされています。相続人とは法定相続人のことをいいますから、配偶者、子、直系尊属がこれにあたります(民法886条以下)。なお、兄弟姉妹は法定相続人にあたりますが、遺留分権利者の対象からは除外されていることに注意が必要です。
1項各号は、総体的遺留分の割合を定めています。総体的遺留分とは、遺留分権利者全体に遺されるべき、遺産全体に対する割合をいいます。
1号では、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、2号では、その他の場合は2分の1であるとしています。
ところで直系尊属とは、被相続人の父母や祖父母など、家系図でみて被相続人よりも上の代の方を差します。
2項では、個別的遺留分について定めています。総体的遺留分は、いわば相続人全員分として保障される金額になりますが、個別的遺留分は、その全員分を一人一人に分配した場合の金額を指します。2項は、具体的には遺留分権利者の法定相続分の割合をかけた額が実際の遺留分金額(個別的遺留分)になるとしています。法定相続分の割合は民法900条で定められています。
1043条(遺留分を算定するための財産の価額)
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
1044条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
1043条と1044条は、遺留分を算定するための財産の価格について定めています。
1043条1項は、遺産金額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額+贈与した財産の価額−債務の全額と定められています。なお、「相続開始の時において有した財産」とは、積極財産を意味し、遺贈や死因贈与された財産もここに含まれます。
そしてこの「贈与した財産」の贈与は何をさし、いつまで遡るべきかについては、次の1044条に規定されています。
算入の対象となる贈与は、相続人に対してされた贈与に限られません。そして相続人に対する贈与は原則として相続開始前の1年間(1044条1項前段)が、相続人以外の者に対する贈与は原則として相続開始前の10年間(同条1項前段、3項)が対象となります。
さらに、「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って」した贈与は、上記の期間制限に関わらず算入の対象となります(同条1項後段) 。
1045条
負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
2 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。
1045条は、負担付贈与がされた場合はどの範囲を贈与の価額に含めるかについて定めたものになります。負担付贈与とは、一定の義務を負担させる贈与をいいます。例えば、家屋を贈与するけれども、ローンが残っている場合や、山林を一部贈与する代わりに、隣接する贈与者の山林を管理してもらうような場合がこれに当たります。
1045条は、1043条1項に規定する贈与財産の価額は、負担付き贈与の場合、贈与の価額から負担の価額を控除した額を算定の基礎に入れることを規定しています。つまり、3000万円相当の家屋に、500万円のローンが残っているような負担付贈与では3000万円=500万円=2500万円を含めることになります。なお、同条2項で規定しているような、不相当な対価による有償行為であって、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたものについては、負担付贈与とみなすことにされています。つまり、贈与にしてしまうと遺留分の算定の基礎にされてしまうから、売買という形式にして譲り渡そうとしたよう場合も、実質的にみてそれは贈与なのだから、負担付贈与とみなしてしまうことで規制を図ろうということです。例えば3000万円相当の家屋を、贈与ではなく1万円で売り渡すなどの場合がこれにあたります。この場合、負担付贈与とみなされるので、3000万円-負担分1万円=2999万円を算定の基礎に含めるということになります。
1046条(遺留分侵害額の請求)
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
1046条は、遺留分侵害額を誰に対してどのように請求できるかを定めています。
1項では、受遺者または受贈者に対して、遺留分侵害額相当の金銭の支払いを請求できるとしています。実はこの点は平成30年度に大きく改正されたポイントで、現物ではなく、金銭的請求ができるという点が改正ポイントです。これにより、旧法下では、例えば建物の1/3の所有権を請求できるという非常に複雑な状況に陥りがちだったものが、建物の1/3相当の金銭を請求できるというものに改正されたことで、非常に簡明な権利行使ができるようになりました。
なお、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者たる相続人が被相続人から得た純財産額が、遺留分額に達しないときに遺留分侵害額請求権が成立します。例えば遺留分額は500万円なのに、そのほとんどが遺言等によって受遺者に移ってしまい、100万円しか相続できなかった、という場合に、受遺者に対して500万円-100万円=400万円を請求できることになります。
請求の相手方は、受遺者・受贈者・その包括承継人です。では、これらが複数人いる場合、誰に請求するべきかを次の1047条が定めています。
1047条(受遺者又は受贈者の負担額)
受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
2 第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。
3 前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
4 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
5 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
1047条は、受遺者又は受贈者の負担額と題して、その負担の順序を定めています。
まず1項1号によると、受遺者や受贈者が複数いる場合、先に受遺者から負担します。
なお、受遺者とは、遺贈を受ける者として遺言で指定された者をいいます。受贈者とは贈与を受けたものをいい、どちらも贈与を受けたものであるようにも思えますが、その贈与原因が遺言である者のことは、特に受遺者という、ということになります。
また、1項2号は、受遺者・受贈者が複数いて、その贈与が同時にされていた場合は、価額の割合に応じて負担します。例えば遺留分権利者から遺留分侵害であるとして500万円を請求されており、受遺者Aは2000万円を、受遺者Bは3000万円の遺贈を受けていた場合、Aは200万円、Bは300万円を支払わなければならないということになります。
受贈者に対する贈与が同時ではなく、時間的な差があってされている場合は、相続開始時に近い時に贈与を受けた受贈者から負担します(1項3号)。亡くなる1ヶ月前に贈与を受けたAさんと、亡くなる2ヶ月前に贈与を受けたBさんでは、Aさんが支払わなければならないということになります。
なお、死因贈与と呼ばれる、贈与者の死亡によって効力を生ずる条件付贈与契約の形式によって贈与がされた場合、これは遺贈ではなく贈与として扱います。
つまり、遺贈→死因贈与→生前贈与の順番で、負担を受けることになります。
1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
1048条は、遺留分侵害額請求権の時効消滅期間について定めています。
これによると相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知ったときから1年間、知らないままであっても相続開始から10年経過すると、遺留分侵害額請求権は時効によって消滅するとされています。なお、「知った」というのが、何を知った場合これに当たるのかについて、単に贈与や遺贈があったことを知っているだけでなく、自らの遺留分を侵害していることを知ったときのことをさすと考えられています。
1049条(遺留分の放棄)
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
1049条は遺留分の権利の放棄について定めています。1項によると相続開始前の放棄は家庭裁判所の許可を受けた時に限って効力が認められます。なお、相続開始後の放棄については明文規定はありませんが、自由に認められると考えられています。また2項では、遺留分の放棄は他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさないと定めています。つまり、他の共同相続人の遺留分まで放棄されてしまったり、また遺留分権利者が減ったからといって他の共同相続人の個別的遺留分が増加するわけではないことを確認しています。この理由は、遺留分はあくまで個人の財産権であり、相続財産のように共有にあるものではないからです。
1050条
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除に
よってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
1050条は、民法最後の条文です。遺留分に関する規定ではなく、特別の寄与という制度について定められています。これは、平成30年度の改正で新たに新設された規定です。
改正前は、相続人の対象ではない親族が、被相続人に対して療養看護や身の回りのお世話をしていたとしても、遺言や贈与がない限り、相続財産を取得することができませんでした。そこで、新たに1050条を新設することで、相続人以外の親族であっても、無償で療養看護その他の労務提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与を場合には、その寄与に応じた額の金銭の支払を相続人に対して請求できるようになりました。
まず、1項では、特別寄与者に対して、各相続人は寄与に応じた特別寄与料を支払う規定されています。なお、特別寄与者は親族が対象であり、相続放棄をした相続人や、欠格・廃除によって相続権を失ったものはこれに含まれません。
2項では、特別寄与料についていくら支払うべきかなどの協議ができなかった場合は、家庭裁判所に対して協議に変わる処分を請求することができるとしています。家庭裁判所はこの請求を受けると、寄与の時期や、方法及び程度など様々な事情を考慮して、特別寄与料の額を決定します(3項)。
なお、同項ただし書にあるように、家庭裁判所に対する特別寄与料の請求は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から半年以内、またはは相続開始の時から1年内に請求を行なう必要があります。最後に4項では請求金額の上限を定めていて、特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価の価額を控除した残額を超えることができないとしています。